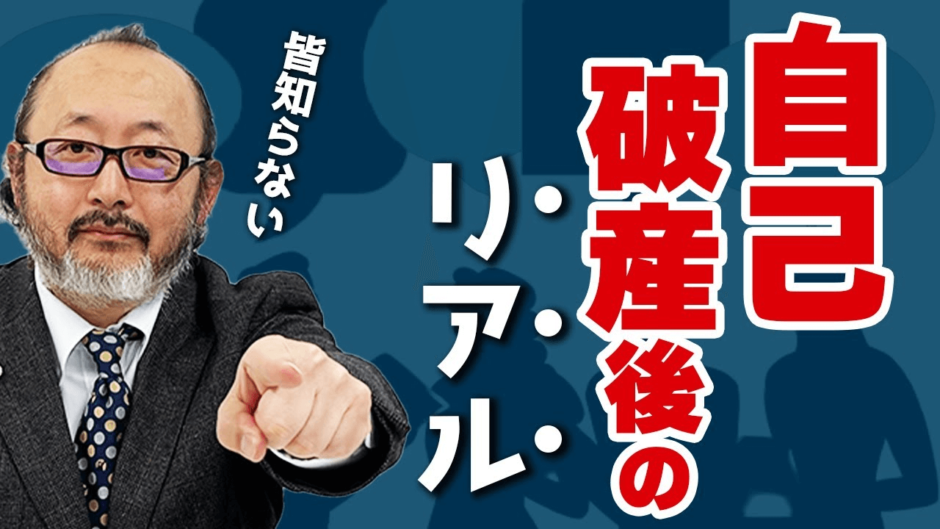みなさんこんにちは、弁護士の杉山です。
自己破産は借金を0円にできるという大きなメリットがありますが、その一方で自己破産をしたその後の生活はどう変化するのか不安に思っていませんか?
そこで今回は、自己破産すると実際はどんなことが起き、どんな生活が待っているのか、について解説します。
自己破産をしようか迷っている方や、自己破産をしたいけどその後の生活が気になってなかなか決断できないという方、ぜひ参考にしてみてくださいね。
自己破産とは?

自己破産とは、債務整理の手法のひとつで、裁判所に申し立てることによって、借金の額をゼロにしてくれる制度です。
その一方でデメリットもあります。家や自動車、貴金属などの、価値の大きな財産は手放さなければなりません。
また、一部の職業に就くことができないという就労制限もあります。
債務整理には他に、任意整理と個人再生があります。
それぞれについて興味のある方は
「【債務整理】あなたに向いている債務整理を教えます。債務整理の種類を徹底解説!」
の記事をご覧ください。
破産制度について解説
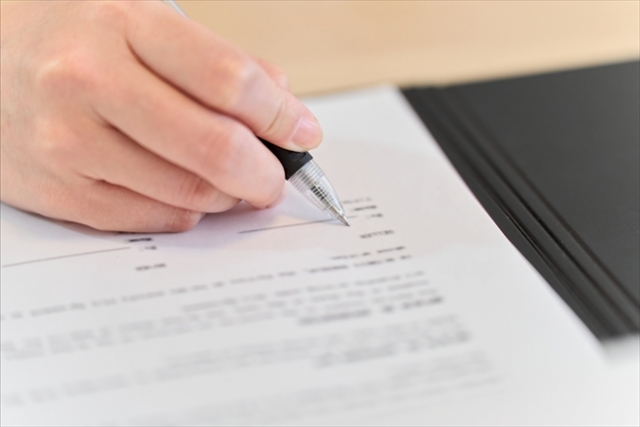
破産制度は債務の返済が全くできなくなってしまった「支払不能」という状態の債務者が利用できる制度です。
自分の財産を投げ出して債務を精算し、それでも残った債務は支払義務を免除し、新たな経済活動を始められるようにする制度です。
単に借金を返済したくなくなったという理由で利用できるものではありません。
破産手続きは2種類!同時廃止と管財事件って何?

では、破産制度を利用した場合に、その債務者に生じる生活上の制限にはどのようなものがあるでしょうか?
これには、「破産手続き中の制限」と「破産手続き後の制限」とがあります。
そして、破産手続き中の制限は、「同時廃止」の場合と「管財事件」の場合とでは大きく状況が異なります。
まずはこの2つの違いから解説していきます。
同時廃止
破産の手続きは、債権者のための精算手続きと債務者のための免責手続きの二段階で構成されています。
第一段階は債務者の財産を利用して債権者にできる限りの支払いを行う精算手続きです。
もし債務者の財産が無い場合、裁判所は破産手続きを開始すると同時に終了させる「同時廃止」の決定をします。
この「同時廃止」の場合、あとは債務をゼロにするかどうかを決める手続き、つまり免責を許可するか不許可とするかを判断するだけとなります。
管財事件
これに対して、債務者が家、自動車、貴金属、有価証券などの大きな財産を持っている場合、その財産はお金に換えて債権者に公平に分配します。
この場合、第一段階の精算の手続きをする必要があり、この場合を「管財事件」と呼びます。
管財事件の場合、破産管財人が債務者の財産を調査、管理、売却して集めたお金を債権者に分配します。
当然のことですが、「管財事件」の手続きは「同時廃止」の場合よりも時間がかかります。
自己破産手続き中の義務と制限について

自己破産は、借金苦から債務者を救済する債務整理方法の1つです。
ですがその一方で、さまざまな義務や制限が課せられます。
自己破産手続き中の義務
破産手続中には以下のような義務が課せられます。
① 破産者に対して、重要な財産を開示する義務
② 破産管財人に対して説明する義務
③ 裁判所や破産管財人の調査に協力する義務
このように、破産者には、破産手続や免責手続において、破産管財人や裁判所に対して説明したり、その調査に協力する義務があります。
自己破産手続き中の制限
次に、破産手続き中の制限について説明していきます。
破産法が課している制限としては以下の3つがあります。
① 居住地の制限
② 郵便物等の破産管財人への転送
③ 就労制限
それぞれ詳しく解説していきます。
① 居住地の制限
財産隠しや逃亡を防止するために、裁判所の許可なく、居住地を離れることを禁止しています。
そのため、破産した人が、破産手続中は引っ越しをしたり、宿泊を伴う旅行をしたりするには裁判所の許可が必要とされます。
これは仕事上の出張であっても同様です。
② 郵便物等の破産管財人への転送
裁判所は、破産者宛ての郵便物等を破産管財人に転送する措置をとることができます。
この場合、破産管財人は、その郵便物等を開けて、内容を見ることができます。
ですから、破産制度を利用した場合、破産手続中は、このような生活上の制限を受けることについては、あらかじめ知っておく必要があります。
③ 就労制限
破産手続中は、一部の職業に就くことができないという就労制限もあります。
まず、弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士などがあります。
意外に感じられ、多くの人にも関係があるのは、次の4つです。
① 宅地建物取引業者・宅地建物取引士
② 古物商
③ 警備員
④ 生命保険の募集員・損害保険の代理店
もっとも、これらの就労制限は、免責許可決定が確定すれば外れます。
また、破産による資格の制限としては、年金の受給権や選挙権などの権利が制限されることはありません。
自己破産後に起こる生活の変化

次に、破産手続が終了し、免責許可決定を受けた後の生活の変化についてです。
第1に、それまでの借金の支払い義務はなくなり、借金はゼロになります。
しかし、一部、免責されない支払義務もあります。それは以下の通りです。
・租税や罰金の支払義務
・悪意で加えた不法行為による損害賠償義務
・故意または重過失によって他人の生命や身体を害した不法行為の損害賠償義務
・婚姻費用や養育費などの支払義務
第2に、就労上の資格制限などについては、免責によって当然に復権しますので、制限はなくなります。
第3に、新たな借入れや、クレジットカードを作ることは、しばらくできません。
これは、いわゆる「ブラックリストに載った」という状態になるので、その効果です。
以上のように、自己破産手続が終了した後には、新たな借入などはできないものの、借金の返済に追われることのない生活を送ることができるようになります。
自己破産後の生活で陥りやすい危険

みなさん意外に思われるかもしれませんが、破産手続が終わった途端に「お金を貸します」という誘いが来ることがあります。
もちろん、そういう業者は、まともな業者ではありません。
ありえないような高利でお金を貸し、厳しく取り立てをしてくるような業者です。
では、そういう業者は、なぜ破産をした人にわざわざ金を貸すなどと言ってくるのでしょうか?
理由は以下の3つです。
① 他に債権者がいなくなっているから
② ふつうの業者からは新たに借金ができないから
③ 破産から7年間は再度破産をして免責することができないから
だから、お金を貸しても、破産免責によって取りっぱぐれになるという心配がないので、わざわざ破産手続が終了したばかりの人に「お金を貸します」と言ってくるのです。
ですから、破産をして、免責を受けた後の生活では、このような危険に十分注意してください。
まとめ
いかがでしたか?今回は「自己破産をした後の生活」について解説してきました。
自己破産は、借金苦から債務者を救済する債務整理方法の1つですが、さまざまな義務や制限が課せられます。
就労制限については、特に、不動産業、中古品販売業、警備員、保険の外交員や代理店の方は注意する必要がありました。
また、債務整理をしたことで、悪質貸金業者からの借金の誘いがあるので、そういう誘いには絶対に乗らないよう、注意しましょう。
本記事の内容が少しでもお役に立っていれば幸いです。