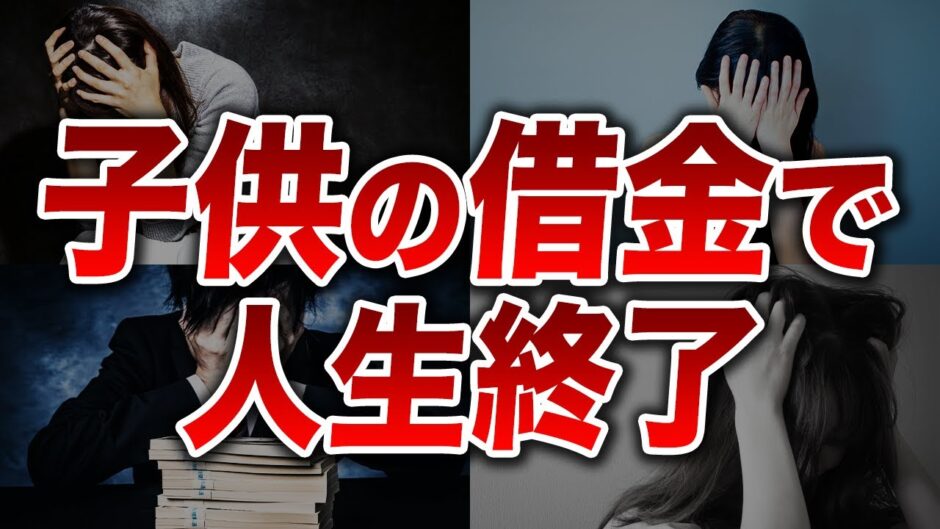みなさんこんにちは、弁護士の杉山です。
家族の誰かが借金をしていたなんてことを想像したことはありますか?
もし思いもよらずそのような事実が発覚した場合、焦って対応してしまったり、どうしてよいのかわからず、途方に暮れてしまう、という人も少なくないと思います。
そこで今回は、子どもが知らぬ間に多額の借金を抱えしまっていた場合に、親としてはどのような責任があるのか、
また、子どもが抱えてしまった借金問題について親はどのくらい関与すべきなのか、
さらには、子どもや家族が抱えてしまった借金問題についての対処法について、現役の弁護士である私、杉山が、わかりやすく解説します。
家族が多額の借金を抱えていたことがわかり対処に困っているという方、事前に家族の借金問題についてどう対処したらよいのか知っておきたいという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
子どもが借金するとどうなる?

まず、子どもが親の知らないうちに多額の借金を作ってしまうのは、どのような場合かということについて考えてみましょう。
大きな借金を作るということになると一般に考えられるのは、消費者金融からの借入や、クレジットカードによるショッピングやカードローンでしょう。
消費者金融の場合、借入ができるための条件としては、「20歳以上で安定した収入のある人」という基準が採られていることが多いです。
一方、クレジットカードの場合の申込みの条件は、「18歳以上」というものが大半です。
大学生や専門学校生の場合は「学生カード」というものが用意されている場合もあります。
そうすると、親の知らないうちに子どもが多額の借金を作ってしまっていたというのは、少なくとも18歳以上、また、消費者金融からの借入となると20歳以上の場合となります。
この年齢になると、クレジットカードによるショッピングやカードローン、消費者金融からの借入により、親の知らないうちに子どもが借金を作ってしまい、自分では解決できない事態に陥っているということも考えられます。
子どもが借金した場合の家族への影響

次に、親の知らないうちに子どもが多額の借金を作ってしまったものの、約定どおりに返済することができず、借金を滞納しているという状態になってしまった場合についてです。
その場合、家族にどう影響するのかについて解説します。
まず、借金を作った子どもが、返済を滞納した結果、そのことが他の家族の信用情報を傷つけるというようなことはありません。
個人信用情報機関のデータベースに事故情報として登録されるのは、借金の返済を滞納したその子どもだけです。
家族だという理由で、信用情報に傷がつき、クレジットカードが作れなくなったり、借入ができなくなったりする、というようなことはありません。
次に、子どもが作ってしまった借金について、親や兄弟姉妹が責任を負うか、ですが、兄弟姉妹だけでなく、親も基本的には責任を負いません。
その子どもの借金が、親や兄弟姉妹に影響することがあるとすれば、次の2つのいずれかの場合です。
子どもの借金の保証人になっていた場合
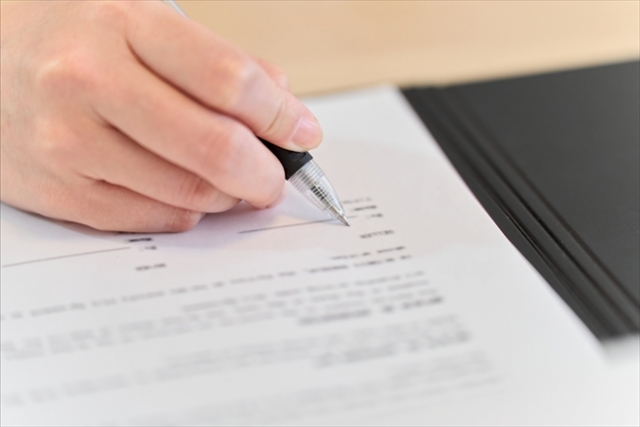
第1は、保証人や連帯保証人になっていた場合です。
いずれの場合も、借金を作ってしまった子どもと同じだけの責任を負うことになります。
保証人と連帯保証人は、いずれも、保証の対象となっている人、この人のことを「主たる債務者」と言いますが、この主たる債務者が借金の支払いをしない場合に、代わって支払う責任を負います。
保証人と連帯保証人の違いは、保証人の場合には、債権者がいきなり保証人に請求してきた場合には、債権者に対して「先に主たる債務者のほうに請求してください」と反論することができます。
主たる債務者に財産がある場合には「先に主たる債務者の財産に強制執行してください」と反論することができるという点です。
これは、法律上「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」と呼ばれているものです。
そして、連帯保証人の場合には、これがありません。
ですから、債権者が主たる債務者ではなく、いきなり連帯保証人に請求してきた場合でも、
これに対して「先に主たる債務者に請求して」などとは言えないことなどが、単純な保証人との違いです。
保証にせよ、連帯保証にせよ、保証をする場合は、債権者との間で保証契約をする必要があります。この保証契約は、必ず書面等でしなければならないと民法によって決められています。
つまり、保証契約書に署名したり、判子を押したりしなければ、自分でも知らないうちに連帯保証人になっていた、なんて事態にはなりません。
保証契約を結んでいない場合、通常の債権者であれば、子どもの借金について、親に対して請求してくる、ということ自体がありません。
逆に、何ら保証契約を結んでいないのに、親のところに請求してくる債権者がいるとすれば、それは次の2つです。
闇金で借金した場合
1つは、闇金などのタチの悪い貸主の場合です。
この場合の対処法としては、法律上支払う義務がない以上、毅然として要求をはねつけることです。
家にまで押しかけてきたり、何らかの嫌がらせを受けた場合には、警察に通報しましょう。
相手方が闇金であれば、「自分にはそんなもの支払う義務はない。もう電話を掛けてくるな」と毅然と振る舞うことが大切です。
闇金の場合は、そもそも違法なことをしているので、裁判所を通じた正当な方法による
強制執行などの手続きをとることはできません。
せいぜいできるのは、嫌がらせなどによりプレッシャーを掛けてくることなので、
家族がドーンと構えていれば、やりようはないのです。
ですから、子どもをなんとか救いたい、と考えるのであれば、ドッシリと構え、子どもを不安にさせないということが大切です。
それと同時に、弁護士に相談することも、もちろんよい方法です。
保証契約書の署名を勝手に書かれていた場合
次に、親は保証契約を結んでいないのに、債権者が親に請求してくる可能性の2つ目は、子どもが自分で、保証契約書上の親の署名を勝手に書いたり、押印したりした場合です。この場合は、ちょっとやっかいです。
この場合、親自身は、保証契約を締結していない以上、法律上、保証人や連帯保証人としての責任を負うことはありません。
しかし、その反面、子どもがこのようなことをしたということになると、子どものほうが、刑法上の私文書偽造罪、行使罪、詐欺罪に問われる可能性があるからです。
もちろん、親の立場からすれば、子どもが刑事責任を問われるということは、なんとしても避けたいことでしょう。
子どもが刑事責任を受けるくらいなら、自分が署名・押印したことにして、連帯保証人として支払いをしてしまおうか、と考える人も少なくないと思います。
しかし、見方を変えれば、そのような親心を逆手にとって、わざとこのような書面を作らせているという可能性も考えられるのです。
ですからこのような場合は、何より専門家である弁護士に相談することがオススメです。
こういう場合こそ、素人的な判断は禁物です。
子どもが借金中に相続が発生した場合

つぎに、子どもの借金が、親や兄弟姉妹などに影響する第2の場合についてお話しましょう。第2は、相続が発生した場合です。
人が亡くなったときに、その人が持っていた財産を、夫や妻などの配偶者、子ども、親、あるいは兄弟姉妹などが引き継ぐという民法上の制度が相続です。
そして、子どもが多額の借金を抱えているという場合に、相続が発生すると、これによって、他の家族が影響を受けるということがあります。
次の2つの場合が考えられます。
- その子ども自身が亡くなった場合
- 親が亡くなった場合
子ども自身が亡くなった場合
まず、子どもが亡くなった場合ですが、その子ども自身に、子どもがいなければ、配偶者と親が相続人となります。
また、その子どもに配偶者もいなければ、親だけが相続人となります。
この場合、相続によって親は子どもの財産を引き継ぎますが、この財産には、プラスの財産、つまり資産だけではく、マイナスの財産、つまり負債も含まれます。
そこで、多額の借金を負っていた息子や娘が亡くなったという場合、親はその子の借金を相続によって引き継いでしまうことになります。
これに対する対処法ですが、子どもがプラスの財産をほとんどもっていない、という場合であれば、相続放棄をすることです。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったということになるので、プラスの財産も、マイナスの財産も、まったく引き継がないということになります。
ですから、これで多額の借金を支払う義務を引き継いでしまうことを回避することができます。
ただ、この場合、注意点が2つあります。
1つ目の注意点は、この相続放棄は、期間に制限があるということです。それは、自分が相続人になったことを知ったときから、3か月です。
この期間内に家庭裁判所に対して、相続放棄の申述受理の申立てをしないと、相続放棄はできません。
2つ目の注意点は、こうして親が相続放棄をした場合、次は、兄弟姉妹が相続人となり、借金を引き継ぐことになってしまう、ということです。
そこで、子どもの借金を引き継がないために親が相続放棄をした場合は、そこから3か月以内に、次は兄弟姉妹は相続放棄をする必要があるということです。
親が亡くなった場合
次に、多額の借金を負っている子ども自身ではなく、親が亡くなった場合を考えてみましょう。
たとえば、親が亡くなり、Aさんには、奥さんのB子さんと2人の息子CとDがおり、Aさんの財産は、自宅の土地建物だけだったとしたます。この場合にAさんが亡くなり、息子の1人、Dに多額の借金があったとするとどんなことが起こるでしょうか。
遺産である土地・建物を相続するのは、B、C、Dの3者です。
割合は、Bが2分の1、CとDはそれぞれ4分の1ずつとなります。そうすると、土地と建物の4分の1は、Dの財産ということになるので、Dが借金の返済をしない場合、最終的に、債権者は、Dの持分である土地・建物の4分の1を差し押さえて、競売に掛けることができます。
もちろん、土地・建物の全体ではなく4分の1の持分だけ、ということになると、わざわざこれを買おうという人は少ないかもしれません。けれども、あえてこれを買おうという人が現れた場合、これはどんな人でしょう?結構面倒なことになることが予想されます。
もちろん、このような面倒なことになることを避ける対処法も存在します。
それは、Dが相続放棄をすることです。そうすれば、Dは、Aの残した土地・建物の4分の1を相続することはなくなり、B子とCだけが土地・建物を2分の1ずつ相続することになります。
そのため、Dの債権者が、この土地・建物を差し押さえて競売にかけることはできなくなります。
ただ、相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所での手続を執らなければならない、という制限があります。
また、Dが相続放棄という手続きを知っているか、仮に知っていたとしても、その手続きを執るか、という問題もあります。
Dが相続放棄をすることを拒否すれば、これを無理にさせることはできません。
そこで、こうした事態が予想される場合には、Aさんとしては、自分が生きているうちに何らかの手を打っておく方がよい、ということになるでしょう。
もちろん、こうした問題は、それぞれの事案によって最良の解決方法は異なりますので、専門家である弁護士に相談することがオススメです。
子どもの借金問題への対処法
最後に、自分の知らないうちに、子どもが多額の借金を抱えていたことが発覚した場合に、親としてはどのような対応をするのがよいか、
ということについてお話ししましょう。
まず知っておいてほしいことは、法律事務所に借金問題の相談に来る方の中の相当の数の方々が「家族に知られたくない」という希望をもっている、ということです。
子どもの借金問題が発覚したからと言って、頭ごなしに叱りつけたり、借金を抱えることとなった原因を根掘り葉掘り追及したり、「お前には失望した!」などと子どもを見捨てるような発言をしたりすれば、それこそ事態をこじらせ、問題の解決を困難にするでしょう。
もし子どものことを思うのならば、そのような感情はいったん切り離し、とにかく、現在の困った事態を解決するにはどうすればよいか、ということに集中するのが良策です。
次に、子どもの借金問題を解決する方法としては、借金を全額親が支払って、借金をなくしてしまう、というのが1つの最も簡単な方法といえます。しかし、この場合、2つのことに留意する必要があります。それは以下の2つです。
- 子どもの将来の問題
- 兄弟の公平性の問題
子どもの将来の問題
まず、借金問題を親があまりにも簡単に解決してしまうと、子どもとしては、その問題を軽く考えてしまうのではないか、という問題です。
近い将来、また同じことを繰り返し、大きな借金を抱えてしまうことになるかもしれません。それは、その子のためにならないでしょう。
そこで、親自身に経済的余裕があったとしても、解決方法については慎重に考える必要があります。
1つの方法としては、その子どもに、弁護士に依頼して任意整理をさせ、その弁護士費用は親が出すけれども、債権者に対する分割払いは、あくまで子どもにさせる
ということなども考えられます。
実際、私の在籍する法律事務所の依頼者でも、あえてそのような方法を選択する親御さんもいらっしゃいます。
兄弟の公平性の問題
次に、他の兄弟姉妹との公平性の問題です。
子どもの1人が借金問題を抱えてしまい、親がそれを一括返済して解決してあげた場合、
そのことを知った他の子どもたちは、どう感じるかについて考えておくべきです。
というのも、ここでの対処の仕方によっては、兄弟仲を悪くしてしまったり、将来、相続問題が発生したときに、揉める原因を作ってしまうことになるからです。
子どもが複数いる場合、その子たちは、親の愛情というものを常に比較しています。
自分が親から公平に愛情を注がれているか、ということを常に感じ取っています。
仮に、親がその子どもの借金問題を一括返済で解決してあげるとしても、兄弟間の感情について配慮し、何らかの手を打っておく必要があります。
また、経済的余裕が親にない場合でも、子どもの借金問題を解決するために親にできることはたくさんあります。
まず、借金の返済に追い込まれた人は、返済しなければならないのにできない、という
ストレスやプレッシャーで精神的に追い込まれていることが多いです。
そのため、絶対に見捨てたりしない、ちゃんと最後まで解決のために協力してあげる、という姿勢を見せるだけでも、子どもは大いに精神的に救われるはずです。
また、借金問題を解決するための法的な手段である「債務整理」という方法があります。
どうやって解決したらよいのか途方に暮れている子どもに対して、法的な解決方法があるということを教えてあげることも、大きな助けになるでしょう。
そして、親自身が、まずは、法律事務所に電話して相談し、後日、子どもと一緒に改めて相談に訪れるという方もいます。
亀の甲より年の功。金はなくても、知恵がある。借金問題をかかえてしまった子どもに対して親の愛情でできることはたくさんあります。
私が在籍している華鼎国際法律事務所でも、借金問題やその他さまざまな法律問題についての相談や弁護依頼を受け付けています。
公式LINEから簡単にお問い合わせができますので、身近に弁護士の知り合いがいないという方は、ぜひ登録してみてはいかがでしょうか。
まとめ
いかがでしたか?
今回は「子どもが借金を作っていた場合の対処法」についてご紹介しました。
子どもが借金を作っていても、家族への影響は基本的にありませんでした。
例外的に保証や連帯保証をしている場合、また、その子どもが多額の借金を追った状態で、子どもや親が亡くなり、遺産相続が発生した場合でした。
そして、注意点としては、親の感情を直接子どもにぶつけるのではなく、あくまで冷静に、その解決に向けて対処することが大切でした。
また、具体的な解決方法は、親が一括返済するのが最も簡易な方法でした。
ですがその場合、それが子ども自身の将来のためになるのか、他の兄弟姉妹との公平性をどうするのか、ということに留意することが大切でした。
借金問題を抱えてしまった子どもに対して、親のできることは、必ずしも経済的な支援だけではありません。
精神的なケアや債務整理への道筋を付けてあげるなど、臨機応変に対応しましょう。
本記事の内容が、少しでもお役に立っていれば幸いです。