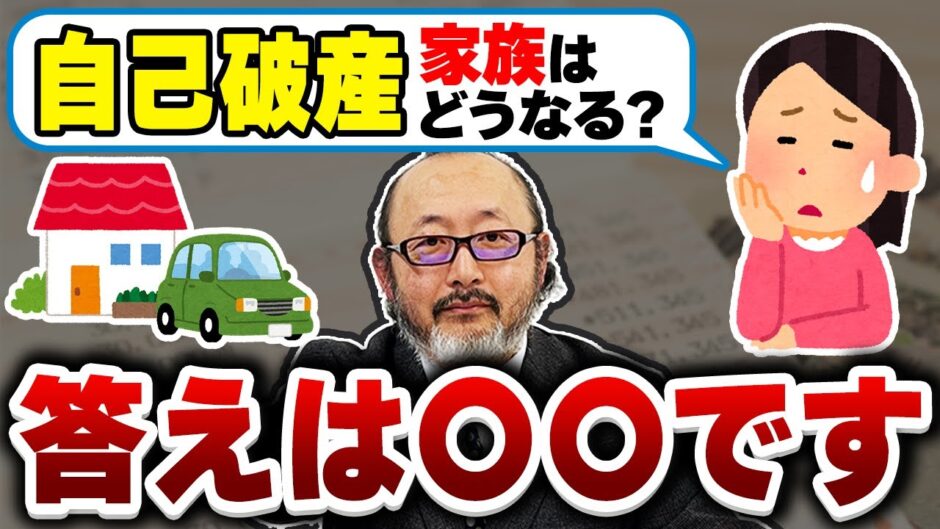こんにちは!弁護士キャリア30年、かなえ国際法律事務所の杉山です。
最近は、借金問題を解決するための法的な手段として、債務整理というものがあることが、多くの人に知られるようになってきました。
個人の方によく利用されている債務整理の方法には、自己破産、個人再生、任意整理の3つがありますが、中でも、自己破産は、借金の額を実質0円にできる可能性がある、最も強力な方法です。
しかし、自己破産には、このような大きな経済的メリットがある一方で、一定のデメリットも伴います。
また、そのような自己破産による影響は、申立をした本人だけでなく、家族などの周囲の人に対しても、一定の影響を伴うこともあります。
そこで、中には、自己破産はしたいけれども、周囲の身内に迷惑がかかってしまうのであればできない、と考える方もいらっしゃいます。
しかし、自己破産をした場合に周囲の人たちに起こる影響とは、一体どんなものなのでしょうか?また、その影響をなくしたり、最小限度にとどめたりする方法はないのでしょうか?
そこで、今回は、自己破産をした場合、本人の周囲の人たちには、実際どんな影響があるのか?そのような影響を最小限度にとどめる方法はないのか?ということを現役の弁護士である私、杉山がわかりやすく解説します。
借金問題がもう限界に近いけれども、周囲に迷惑を掛けてしまうと考えると、自己破産に踏み切ることができないという方、自己破産をした場合には、自分の周囲の人たちにはどんな影響があるのかを知りたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次 非表示
自己破産とは?

まず、自己破産という債務整理の制度についてかんたんに説明します。
自己破産は、債務者が裁判所に対して自己破産の申立をすることによって、裁判所や、裁判所から選任された破産管財人と呼ばれる人によって行われる債務整理の手続のことです。
その時点で債務者が持っている全財産で、債権者に対する債務を可能な限り弁済し、それでも残ってしまった債務については、裁判所による免責許可決定によって、債務者に対して、これらを支払う責任を免除する、というものです。
つまり、債務者が全財産を投げ出す代わりに、それでも残ってしまった債務については、その責任を免除し、債務者が将来に向かってゼロの状態から再起ができるようにしてあげよう、という制度です。
もっとも、全財産と言っても、実際には、すべての財産というわけではなく、債務者が生活を継続していくために必要とされる最低限度の財産は残されます。
債務者が投げ出さなけばならないのは、家や車、高級家電、貴金属などの、売却すればある程度のお金になり、債権者に対する弁済の原資になるような財産です。
いわゆる「身ぐるみ剥がされる」わけではありません。
自己破産した場合の周囲への影響

次に、債務者が自己破産をした場合、その周囲の身近な人たちにはどのような影響があるのか、について説明します。
債務者が自己破産をした場合に影響を受ける周囲の人たちは次のとおりです。
- 配偶者や子どもなどの同居の家族
- お金を貸してくれた親戚や友人
- 連帯保証人になってくれた親戚や友人
それぞれ詳しく解説していきます。
同居の家族への影響
第1に、配偶者や子どもなどの同居の家族です。
自己破産は、先ほども説明したように、債務者が自己の財産を投げ出す代わりに、最終的に残ってしまった借金の額を実質ゼロにしてくれるという制度です。
そのため、同居の家族も、債務者名義の家に住み、債務者名義の自動車を使っているという場合、自己破産をした場合、最終的には、その家を出なければなりません。
車も使えなくなってしまうため、家族への影響が出てきます。
家について、支払中の住宅ローンがある場合には、そのローンに付けられている抵当権が実行されて、家を出なければならなくなります。
自動車についても、ローンで購入し、支払中という場合は、多くの場合には所有権留保が付けられていますので、これに基づいて債権者が引き上げてしまいます。
また、家や自動車について、すでにローンの支払いを終わっているという場合であれば、こんどは、各債権者に対する平等な弁済のための資金とするために、破産管財人が、債務者からこれらを取り上げて、管理し、換価してしまいます。
やはり、最終的には、家族ともども家を出なければなりませんし、車も利用することができなくなります。
また、高級家電などについても、破産管財人によって管理、換価されてしまうため、同居していてこれを利用していた家族にとっては、やはり影響があるということになります。
さらに、自己破産による法律上の効果ではありませんが、債務者について債務整理が始まれば、そのことが信用情報機関のデータベースに事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリストに載った」という状態になります。
そして、こうなると、新たな借入れや、クレジットカードを使うことなどができなくなります。
そこで、配偶者や子どもなどの家族が、債務者名義のクレジットカードの家族カードを使っていたという場合などは、この家族が使っていたクレジットカードも使うことができなくなってしまいます。
ただ、家族である配偶者や子どもが、自分名義のクレジットカードを作ることは問題ありませんし、自分自身の信用に基づいて新たな借入れをすることも可能です。
自己破産をしたことに伴う、このあたりの影響は、どうしたって同居の家族には発生してしまいます。
そして、確かに、自己破産をしたことに伴って、転居しなければならない、ということになれば、家族にとっては大きな生活の変化でしょうし、自動車が生活必需品であれば、それが使えなくなることは困るでしょう。
しかしそれでも、これらの家族への影響については、自己破産をしないという理由にはならないと考えられます。
なぜなら、すでに深刻な借金問題を抱えてしまっているのであれば、たとえ自己破産をしなくても、どこかの時点で、必ず、経済的には破綻し、債権者に対する支払いが滞ることになるからです。
そして、住宅ローンの支払いが滞れば、どこかの段階で抵当権が実行されるでしょうし、住宅ローンなどがない場合には、こんどは他の債権者がこれに強制執行し、競売を掛けてくるでしょう。
そのため、すでに自己破産が必要なほどの深刻な借金問題を抱えてしまっているのであれば、結局は、どこかの時点で、家からは出なければならなくなってしまいます。
また、自動車についても、自動車ローンの支払いが滞れば、どこかの段階で、所有権留保に基づいて自動車を引き上げられてしまうでしょう。
したがって、これらの点は、結局のところ、自己破産をしてもしなくても、いずれは発生してしまう家族への影響なんです。
これらの影響を心配し、自己破産を躊躇していても、結局、遅かれ早かれ起こることなので、あまり意味はないといえるわけです。
なお、住宅については、どうしても手放したくない、という思いがあるのであれば、自己破産ではなく、個人再生によって債務整理するという方法を検討する余地があります。
この点については、「【個人再生】個人再生のメリットデメリットを解説。個人再生考えている人必見!」こちらの記事で詳しく解説しています。
興味のある方は、ぜひそちらもご覧ください。
お金を貸してくれた親戚や友人への影響
次に、債務者が自己破産をした場合に影響を受ける人の第2は、これまでお金を貸してくれた親戚や友人などです。
自己破産は、破産開始決定の時点で、債務者が持っていた財産によって、すべての債権者に対して、足りないながらも平等な弁済を実現しようという制度です。
そのため、その対象となる債権者は、すべての債権者であって、一部の債権者を除外したり、一部の債権者についてだけ有利な扱いをすることは法律が特に認めている場合を除いて、できません。
しかし、債権者の中には、クレジットカード会社や消費者金融などだけでなく、経済的に困ったときに、お金を貸してくれた親戚や親しい友人などが含まれていることもあります。
そして、債務者も、そういう人にお金を借りるときには、「絶対に迷惑をかけないから」などと言って、頭を下げて借りたということもあるでしょう。
そのため、債務者の中には、そういう人たちにだけは、どんなことをしてでもお金を返したいと考える人も少なくありません。
しかし、各債権者を平等に扱うということは、破産制度の最も重要な理念です。
そのため、債務者にどんな気持ちがあろうと、そのような親戚や友人だけを有利に扱うということはできないとされています。
そうすると、じゃあ、自己破産の申立をする前に、そういうお金を借りた親戚や友人に対してだけ先に返済をしてしまったらどうだろう? と考える人がいるかもしれません。
こういう、破産開始決定の前に、特定の債権者に対してだけ弁済をする行為を「偏頗弁済」や「偏波行為」などと言います。
もちろん、偏頗弁済は、債権者の平等を害する行為として、破産法上禁止されています。
特に、もはや自己破産することがやむを得ないというような経済状態になったあと、せめて親戚や友人にだけは借金を返済してしまおうなどと考えて、これらの債権者に対してだけ、その時にあった現金や財産をかき集めて返済した、などという場合には、破産手続が始まった後に問題となります。破産管財人が、これらの行為に対して、否認権という権限を行使して、債務者の財産状態を、それらの行為が行われる前の原状に回復させる、ということが行われます。
そして、更に悪いことには、債務者がこれらの偏頗行為をした場合、状況によっては、その後に、裁判所による免責許可決定がなされなくなってしまうということがあります。
もちろん、自己破産をしても、免責が許可されなければ、借金が実質ゼロになるという効果はありません。
つまり、債務者の立場からすれば、自己破産をしたことがまったくの無駄になる、と言えます。したがって、もはや自己破産をすることはやむを得ないというほどに借金問題が深刻な状態に至ってしまったら、親戚や友人に対してだけ優先して借金を返してしまう、などということは、絶対にすべきではありません。
しかし、そうは言っても、一番苦しい時に自分を支援してくれた親しい人たちに、絶対に迷惑を掛けませんと約束してお金を借りたのに、自己破産をしてその人たちに迷惑を掛けてしまうことは耐えられない、という人もいるでしょう。
では、そういう場合はどうしたらよいのでしょうか?
この場合、破産手続については、あくまですべての債権者に対して平等・公平に行われる必要があります。
そして、その結果、裁判所による免責許可決定がなされたら、その効果として、法律上例外とされている債権を除いて、すべての残った債権について債務者は、支払をする責任を免除されます。
これが、免責の効果です。
インターネット上では、このことをもって「借金がなくなる」「債務が免除される」などという表現もよく見られるところです。
しかし、法律上の厳密な話をすれば、実は「借金がなくなる」わけでも「債務が免除される」わけでもないんです。
実際には、債務、つまり借金は、依然として存在しているんだけれども、それを支払うことが強制されない状態になります。
つまり、それを支払うか、支払わないかは債務者の自由であるという状態になる、と考えられています。このような債務を、法律の専門用語では「自然債務」と言います。
つまり、裁判所の免責許可決定がなされると、残った債務は「自然債務」になるとされています。ということは、どういうことでしょうか?
つまり、免責許可決定がなされた後、残った債務について支払うか支払わないかは、自己破産をした人の自由ということです。
そのため、親戚や親しい友人などから借りたお金については、どうしても返したい、これらの人たちに迷惑をかけたくない、というのであれば、破産手続がすべて終わった後に、これらの人たちにだけ、新たに働いて得た財産で、弁済するということは、自由だということです。
したがって、自己破産をすることでこれらの人たちに迷惑を掛けることは、どうしても心苦しい、と考えるのであれば、最終的には、すべてが終わった後で任意に返済をすればよい、ということができます。
連帯保証人になってくれた親戚や友人への影響
最後に、債務者が自己破産をした場合に影響を受ける人の第3として、金融業者などからお金を借りる際に連帯保証人になってくれた親戚や友人などについて考えてみましょう。
自己破産の手続によって、債務者が免責され、残ってしまった債務について支払う責任を免除されて、実質的に借金がゼロになったとしても、その効果が及ぶのは、自己破産をした債務者だけです。
債務者が、金融業者などからお金を借りる際に連帯保証人になってくれた親戚や友人などに対しては、その効果は及びません。
そのため、債務者が自己破産の手続をとれば、あらかじめ連帯保証人を付けていた債権者は、その連帯保証人に対して、債務の返済を請求することになります。
つまり、連帯保証人に対して、債権者から、残債務の全額を支払ってくれ、という請求が行くことになります。
では、これに対しては、どうしたらよいのでしょうか?実は、どうしようもないんです。
債権者から連帯保証人に対して請求が行なわれることは避けることができません。なぜなら、まさに、こういうときのための連帯保証人だからなんです。
そのため、債権者は、連帯保証人に対して、主たる債務者が支払うはずだったお金を請求し、もし任意に支払わない場合は、民事訴訟を起こし、最終的には、連帯保証人の個人財産を差し押さえて、そこから債権の満足を受ける、ということになります。
これは、連帯保証人にとっては、大きな痛手であり、債務者によって被った大きな迷惑であると言えるかもしれません。
しかし、連帯保証人になる、ということは、究極的には、そういう痛手を負い、迷惑をかけられる、という場合もあることを覚悟するということなのです。
ただ、自分が困っているときに快く連帯保証を引き受けてくれた親戚や友人に対して、どうしても申し訳ないと考えるのであれば、これも、第2の「お金を貸してくれた親戚や友人」の場合と同様に、破産手続が終わった後にでも、その人たちが債権者に対して返済した分を、任意に支払えばよいのです。
このことも、また、第2の場合と同様に、債務者の自由だからです。
そのため、自己破産をした場合、第2のような、お金を貸してくれた親戚・友人や、第3のような、連帯保証人になってくれた親戚や友人などには、一旦は、迷惑を掛けてしまうことになるかもしれません。
しかし、どうしても、それでは、気持ちがおさまらない、顔向けができない、と感じるのであれば、破産手続が終わった後、自分の経済状態が正常に戻ってから、新たに形成した財産を原資として、いくらでも罪滅ぼしもできるし、さらには恩返しをすることもできる、ということです。
まとめ
今回は、自己破産をしたことは、債務者の家族や親戚、友人などには、どのような影響や不利益があるのか、そのような影響や不利益に対しては、どのように対処すればよいのか、またこのような影響や不利益を最小限度に抑える方法はあるのか、ということについて解説しました。
私が在籍しているかなえ国際法律事務所でも、借金問題やその他さまざまな法律問題についての相談や弁護依頼を受け付けています。
公式LINEから簡単にお問い合わせができますので、身近に弁護士の知り合いがいないという方は、登録してみてはいかがでしょうか。
借金問題は、身近な人にはかえって相談しづらい面もあります。
そのために一人を抱え込んでしまうことの孤独感も、借金問題のもう1つのつらい側面です。一人で悩まず誰かに打ち明けることだけでも気持ちが楽になるということがあります。
ですから、独りで抱え込まず、見ず知らずの法律事務所に打ち明けてみてはいかがでしょうか?
そして、その小さな一歩が、あなたの抱えている問題を解決するための、小さくて大きな一歩になるのです。些細なことでもぜひLINEを送っていただければと思います。
また、LINE登録頂いた方には債務整理をするべきかがわかるチェックシートをお送りさせて頂いております。
「いま、自分は債務整理するべきなのかわからない…」といった方は是非ご活用ください。